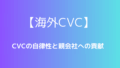CVCの組織形態として本体投資かファンド組成かという選択肢がありますが、欧州のあるCVCでは親会社を唯一のLPとしてファンドを組成しています。その理由としては、投資の意思決定も含めCVCの高い自律性を確保することと高い財務リターンを実現するために経験豊富なVC人材を採用できるような報酬体系を提供するためです。
CVCが高い自律性を確保するために、この親会社ではCVCを特定のビジネスユニット(BU)の配下には設置しないということに配慮しています。この理由としては、BUのような短期的に取り組むべきビジネスを持っているチームが、 CVCのような長期的な思考を持つチームを管理すべきではないという考えがあるようです。このCVCでは、投資に専念するチーム(投資チーム)と投資先を親会社につなぐことに専念するチーム(支援チーム)が存在します。投資チームは投資の意思決定については親会社の承認をまったく必要としません。投資選定における唯一の制約は「親会社の将来にとって重要な分野」に投資をすることであり、そのような分野における最高に有望なスタートアップへ投資することに専念しています。
ファンドとして高い財務リターンを実現するためには、最高に有望なスタートアップに投資をしてエグジットまで持って行ける経験豊富なVC人材が必要となりますが、多くのCVCでは成果連動型報酬の導入が難しいため、そのような人材の確保が課題となっています。このCVCでは、この課題を解決するため通常のVCファンドと同じような報酬体系(キャリー含む)で運用されているようです。財務リターン重視の姿勢は、このような成果連動型報酬の導入を正当化するために必要なものとなっています。
このCVCの親会社は製造業であり、ベンチャークライアントモデルを担当しているチーム(VCM)を設置していますが、CVCとはそれぞれ独立しながらも高度に補完し合う組織になっています。CVCの目的が「財務リターン+戦略的洞察」であり、VCMの目的は「イノベーション導入+内部課題解決」となっており、それぞれの目的に沿って役割分担しています。
CVCにとって報酬制度は難しい課題です。成果連動型報酬が実現できないと実績のあるVC人材は自由度も高くキャリーも提供される通常のVCファンドを選択することになります。ただ、これはCVCの目的として財務リターンの実現をどう考えるかということと深く関連していますので、ここに焦点がないとするとこの課題がクローズアップされることは多くないのかもしれません。
親会社と連携するための組織として、海外では支援チームをCVC内に設置するケースが多い印象ですが、国内のCVCではその機能の一部を親会社のコーポレートベンチャリング(CV)のチームとして設置されるケースもあります。この場合、CVチームにとってCVCは情報源の1つとなり、CVチームはその他の情報のソーシングも行いながら親会社との連携を模索することになります。
海外CVCにおける制度設計