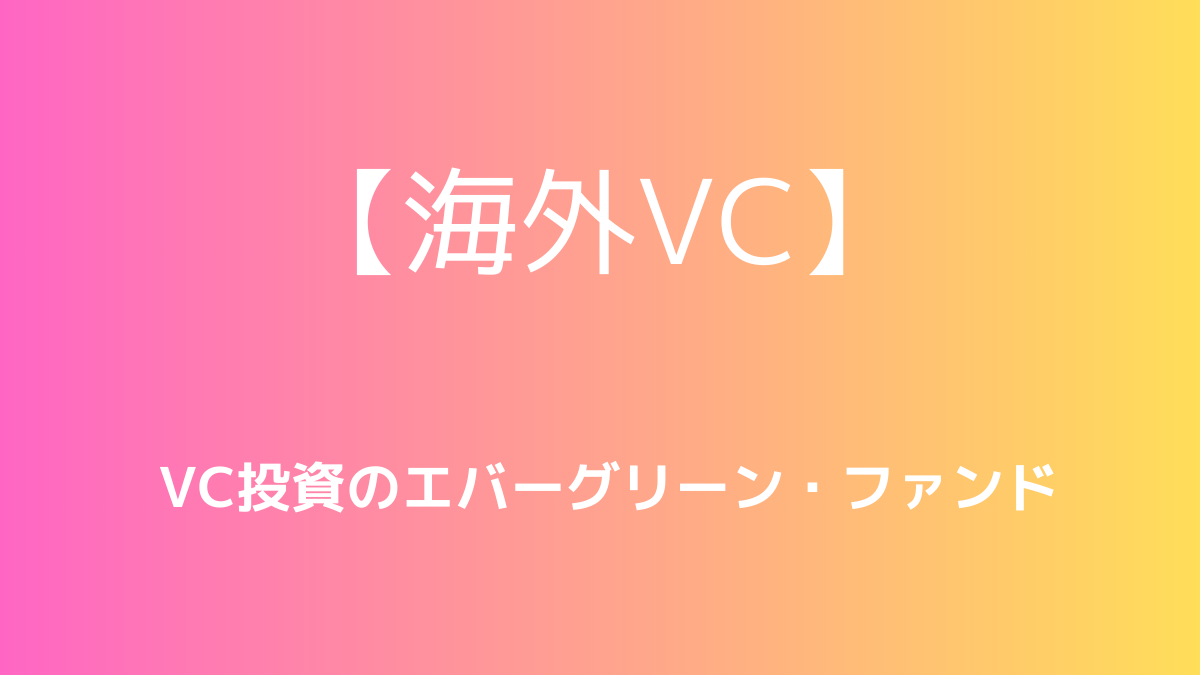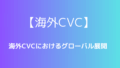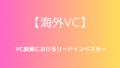最近、オルタナティブ投資運用会社などがVC投資を対象としたエバーグリーン(オープンエンド)・ファンドを組成しているようです。エバーグリーン・ファンドとは従来のVCファンドのような存続期間のあるクローズドエンド・ファンドとは異なり、ファンドの期限を限定せずに、利益を再投資するなどして、投資を継続していくファンドの仕組みです。米国では通常のVCでもエバーグリーン・ファンドに移行しているところもあります。エバーグリーン・ファンドは、LPにとっては柔軟な流動性、長期的投資期間、長期的リターンの実現などの潜在的なメリットが考えられる一方で、明確なエグジット戦略の欠如、流動性リスク、ガバナンスの欠如などのリスクも考えられます。ある運用会社のVC投資を対象としたエバーグリーン・ファンドでは、ベンチャー投資とグロース投資を投資対象として、損失を限定しつつ非対称的なリターンプロファイルを生み出すように設計しているようです。ダンベル型のポートフォリオと言えるかもしれません。ベンチャー投資については通常のVCとの共同投資、グロース投資ではセカンダリー取引を主なディールソースとしているようです。VC投資にとって流動性の改善が遅れている中で、セカンダリーは今後も増加すると予想されています。
CVCの視点から見たときに、上記のエバーグリーン・ファンドの取り組みは下記の2つの点で参考になるのではないかと思います。
(1) 投資対象をベンチャー投資とグロース投資としている
(2) 利益(回収)を再投資することで長期的なリターンを実現する
(1)については、ベンチャー投資をアーリーステージ、グロース投資をレイトステージの投資を想定すると、CVCの投資を小口分散投資と重点投資の2つに分けて実施すると考えることができます。戦略リターンについてはいろいろな考え方がありますが、海外のCVCの取り組みなどを参考にすると、小口分散投資の目的は情報収集やM&Aのパイプライン作り、重点投資の目的は協業実現などの投資先との関係強化と考えることができます。これは戦略リターンに応じて投資の方法を多様化するものであり、その方法の1つとしてダンベル型のポートフォリオは財務リターン実現にとっても有効なものであると考えられます。
(2)については、CVC投資をファンドで行っている場合は、再投資(リサイクル)は限定された範囲内でしか行うことができませんが、本体投資の場合はエバーグリーン・ファンドと同じように考えることができます。CVC活動の財務状況の健全性を維持するとともに将来の投資原資を確保できるようにするために、保有資産(株式)を長期的な視点で保有および処分していることが必要となります。そのために上場株式の継続保有を前提に必要の財務リターンを確保できるように、戦略リターンを考慮した上で新規資産の組み入れおよび保有資産の組み換えを行っていくことが重要となります。
VC投資のエバーグリーン・ファンド