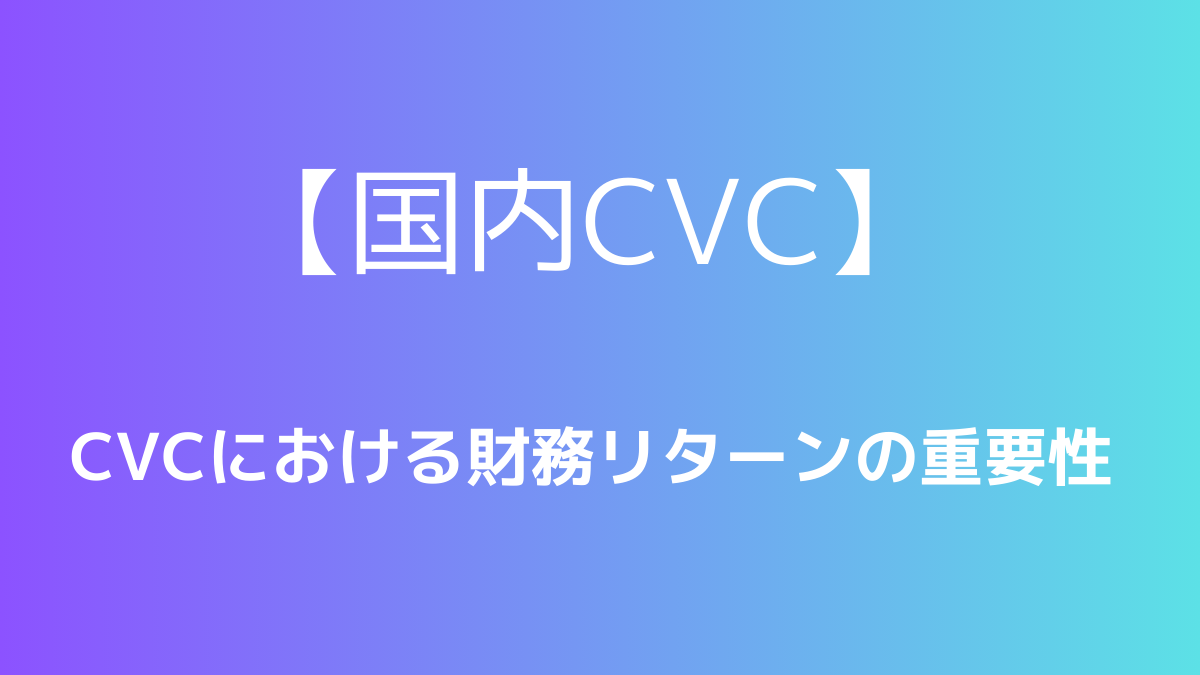CVCにおいて戦略リターンをどう定義してどのように実現していくかという議論は多くの企業でなされている一方で、財務リターンについてはあまり議論されていないケースもあるかと思います。外部VCをGPとしてファンドを組成している場合は、財務リターンについてはGPである外部VCにお任せしているというケースもあるようです。CVCにおいて財務リターンを重視することが重要な理由として、下記のような点が考えられます。
(1) 財務リターンを実現する
(2) スタートアップの成長性を検証する
(3) 利害関係者のインセンティブの整合を取る
(4) CVCの活動に中長期的な視点を与える
(1)については、通常のVCと同じように財務リターンが期待できる案件に投資をしていくということを意味しています。国内のCVCでは戦略リターンを重視しているケースが多いかと思いますが、CVCも投資(出資)という形で親会社の資金を拠出している以上、財務的に健全であることは望ましいのは言うまでもありません。すなわち、CVCが事業として利益を出すということがCVCの事業継続の前提であり、親会社にも財務的な利益をもたらすということになります。
(2)については、財務リターンを重視するということは投資検討時のバリュエーション(企業価値)を評価するということであり、ひいてはその前提になっているスタートアップの事業計画の実効性を検証するということにつながります。CVCとしても成長するスタートアップに投資をしないと意味がなく、その成長の確からしさを財務リターンの検証を通じて行っていることが重要であると考えられます。
(3)については、起業家は会社の持続的な成長を目指しており、その1つの通過点となるIPOにおいて創業者利益を獲得するというケースは多いかと思います。通常のVCは投資先のスタートアップの成長を支援して、IPOあるいはM&Aというエグジットの機会に保有している株式を現金化して財務リターンを獲得することを目指しています。CVCは戦略リターンの実現、すなわち親会社のイノベーションの推進を目的としているケースが多いかと思いますが、起業家や既存株主であるVCとともにそのスタートアップの成長を何らかの形で支援する必要があります。その前提として、そういう利害関係者との共通の目標としてスタートアップの成長とその先にあるエグジットを通じた財務リターンの実現を念頭に置き、投資先のスタートアップにかかわっていく必要があります。すなわち、VCやスタートアップのエコシステムの中で良い投資家であることが重要です。。
(4)については、CVCをファンドで行っている場合はファンドの存続期間(通常10年)は親会社はCVCにコミットしていると考えられますが、本体投資で行っている場合はそういう長期的な視点が不足しているケースもあるようです。CVCの取り組みそのものが親会社の長期的なコミットメントを必要としますが、財務リターンを重視することにより、投資のエグジットを意識し保有している株式の処分方針を決定し、回収した資金の使途(再投資にまわす等)を検討することにより、より中長期的な視点でCVCの活動を推進できることが期待されます。
CVCにおける財務リターンの重要性