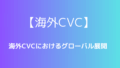企業の無形資産として組織資本と人的資本があるとすると、VCは人的資本への依存度の高いビジネスと考えられます。それは案件のソーシング、DD、モニタリング、エグジットに至る一連のプロセスにおいてVCのパートナー個人の知識、経験などに依存する部分が多いことからも容易に想像ができるかと思います。パートナー個人の専門知識、経験、ネットワーク、案件を見極める能力、起業家と強固な関係を構築する能力は、VCの成功に直接影響します。もちろん、著名なVCでは組織資本としてブランド、各種リソースへのアクセス、投資先の支援体制などを保有しているとも考えられ、それらのVCの投資先ではその後の資金調達、人材採用等においてそのブランドが良い方向に作用することも考えられます。優れたパフォーマンスを達成しているファンドを持つVCは、次のファンドでも優れたパフォーマンスを達成する可能性が高いと言われています。このような点を考慮すると、VCにおいても何らかの組織資本が機能していると考えることもできます。ただ、VC業界においては存続期間10年のファンドという形態が長年にわたって利用され、VCそのものの組織規模も大きくなっていないことを考えると、VCというビジネスは組織資本よりも人的資本への依存度が高いと考えられます。また、パートナー個人の成果と持続性には相関があるようで、過去に成功した経験を持っているパートナーはその後も成功する確率が高いと言われています。 米国ではマーケティング、人材採用等の専門家を社内に配置して投資先に専門的な支援ができるような体制を構築しているVCもありますが、これはVCにおける人的資本の多様化と考えることができますし、組織資本の強化と考えることもできるかもしれません。このVCではその体制を維持するため、ファンド規模が大型化しています。
CVCの母体となっている親会社は規模が大きいケースが多いかと思いますが、大企業では無形資産としては組織資本への依存度が高いと考えられます。大企業では事業を推進するために必要な業務プロセス、リソースなどがいろいろな形で組織資本として蓄積されているため、人事異動(ジョブローテーション含む)で人が変わってもすぐにキャッチアップできるような仕組みが整っているケースが多いかと思います。CVCの組織体制を考える場合に、このような環境の中で人的資本への依存度の高いVCの機能をどのようにCVCに取り込んでいくかということが課題の1つとなります。親会社の社員にはVC投資の実務経験を持った人がいないこと、VC投資の実務経験の持続性などを考えるとVCの機能は社外より獲得し、できるだけ継続的に維持することが重要であると思われます。CVCに関する無形資産と組織体制については、下記のような視点で考えることも意味があるかもしれません。
(1) 戦略リターンの実現(親会社との連携)→組織資本(社内から)→人事異動:有
(2) 財務リターンの実現(通常のVC投資)→人的資本(社外から)→人事異動:無
この考え方は少し乱暴に整理した側面もありますが、戦略リターンおよび財務リターンをどう定義し、どのような体制でどう実現していくのかということを検討する中で、このような視点で考慮すべき点もあるのではないかと思われます。
VCにおける無形資産